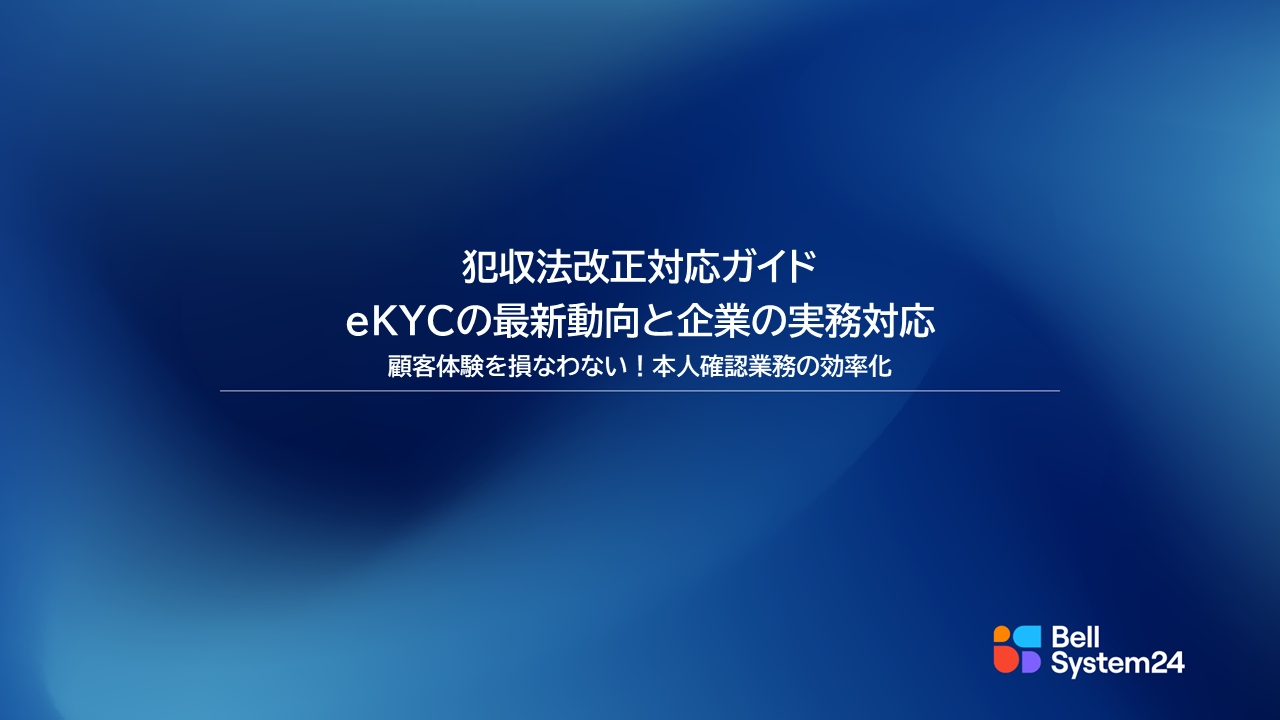2027年4月の法改正に向けて、今から始めるeKYC導入準備。
市場動向から具体的な検討ポイントまで、実用的な情報をわかりやすくまとめました。
サービス詳細はこちらからダウンロード可能です。ぜひをご覧ください。
近年、オンラインビジネスの発展に伴い、マネーロンダリングや犯罪資金の流れを防止する法的枠組みがますます重要となっています。その中心となるのが「犯罪収益移転防止法」です。オンライン決済やデジタル取引が主流となる現代では、非対面取引特有のリスクへの対応が求められています。犯罪収益移転防止法は、オンラインビジネスを含むさまざまな事業者に対して、取引時の本人確認や記録保存などの義務を課しています。しかし、その内容や実務上の対応については、「難しそう」「よくわからない」という声も少なくありません。今回は、この犯罪収益移転防止法について、特にオンラインビジネスを運営する事業者が知っておくべき基本的な知識をわかりやすく解説します。
犯罪収益移転防止法とは?法令の概要と目的
犯罪収益移転防止法(正式名称:犯罪による収益の移転防止に関する法律)は、2008年に施行された法律で、マネーロンダリングやテロ資金供与を防止することを目的としています。この法律は、国際的な資金洗浄対策の枠組みであるFATF(金融活動作業部会)の勧告に基づいて整備されました。
犯罪収益移転防止法の主な目的は、犯罪によって得られた収益が、合法的な資金と混ぜられて「洗浄」されることを防ぐことです。具体的には、金融機関や特定事業者に対して、顧客の本人確認や取引記録の保存、疑わしい取引の届出などの義務を課しています。
この法律がなぜ重要かというと、犯罪組織が不正な資金を合法的な経済活動に紛れ込ませることを防ぎ、犯罪の抑止につなげるという社会的意義があるからです。同時に、テロリズムへの資金供与を防止する役割も担っています。
犯罪収益移転防止法が適用される「特定事業者」とは
犯罪収益移転防止法が適用される「特定事業者」には、以下のような事業者が含まれます。
- 銀行や証券会社などの金融機関
- クレジットカード会社
- 不動産業者
- 宝石・貴金属取扱業者
- 郵便物受取サービス業者
- 電話受付代行業者
- 法律・会計専門家(弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士)
- 暗号資産交換業者
特に近年は、オンラインビジネスやフィンテック企業、暗号資産関連事業者なども対象となるケースが増えており、ビジネスのデジタル化に伴い適用範囲が広がっています。
犯罪収益移転防止法全体を主管しているのは警察庁ですが、特定事業者の事業内容によって、その事業を所管する省庁が法令に基づく監督を行います。
(金融機関なら金融庁、電話受付代行業務と電話転送サービス業務は総務省、など)
事業者に求められる主な義務とは
犯罪収益移転防止法では、特定事業者に対して以下のような義務が課されています。これらの義務を理解し、適切に実施することが法令遵守の基本となります。
取引時確認と本人確認
特定事業者は、法律で定められた特定の取引(特定取引)を行う際に、取引時確認を実施する必要があります。取引時確認の中心となるのが本人確認であり、顧客等の本人特定事項(氏名、住所、生年月日等)を確認しなければなりません。本人確認の方法には以下のようなものがあります。
- 運転免許証やパスポートなどの公的身分証明書による確認
- マイナンバーカードによる確認
- 住民票の写しなど、住所を確認できる書類との組み合わせ
- オンラインでのeKYC(電子的な本人確認)
また、取引時確認では、本人確認に加えて取引を行う目的や職業(個人の場合)、事業内容(法人の場合)の確認も必要です。さらに、法人との取引においては、実質的支配者の確認も求められています。
オンラインビジネスにおいては、非対面での本人確認が課題となりますが、近年ではICT技術の発展により、オンラインでの本人確認手段も拡充されています。
取引記録等の作成・保存義務
特定事業者は、特定取引を行った際の記録を作成し、7年間保存する義務があります。保存すべき情報には以下のようなものがあります。
- 取引年月日
- 取引の種類
- 取引金額
- 顧客の氏名・住所
- 本人確認書類の種類と番号
これらの記録は、後日当局から要請があった場合に提出できるよう、適切に管理する必要があります。クラウドサービスなどを活用した電子的な記録保存システムの導入も一般的になってきています。
疑わしい取引の届出義務
特定事業者は、マネーロンダリングやテロ資金供与に関連する可能性がある「疑わしい取引」を発見した場合、所管行政庁に届け出る義務があります。「疑わしい取引」の判断基準としては以下のような例が挙げられます。
- 顧客の属性や取引の目的に照らして不自然な取引
- 短期間に頻繁に行われる高額取引
- 架空名義や借名取引の疑いがある場合
- 本人確認に協力的でない顧客
これらの判断を適切に行うためには、リスクベース・アプローチに基づいた社内体制の整備が重要です。
犯罪収益移転防止法に違反した場合のリスクと罰則
犯罪収益移転防止法の義務に違反した場合、事業者にはさまざまなリスクや罰則が生じる可能性があります。
法的罰則
犯罪収益移転防止法違反には、以下のような罰則が定められています。
- 本人確認義務違反:2年以下の懲役または300万円以下の罰金(両方が科される場合もあり)
- 疑わしい取引の届出義務違反:2年以下の懲役または300万円以下の罰金
法人の場合、両罰規定により、違反行為を行った個人だけでなく、法人自体にも罰金刑が科される可能性があります。
レピュテーションリスク
犯罪収益移転防止法への対応策と実務上のポイント
犯罪収益移転防止法に適切に対応するため、事業者が取るべき対策について解説します。
社内体制とガイドラインの整備
効果的なコンプライアンス体制を構築するためには、以下のような取り組みが重要です。
- コンプライアンス担当部署や責任者の設置
- 従業員への定期的な教育・研修の実施
- 内部監査体制の構築
- 最新の法令改正情報の収集と対応
特に中小企業や新興のオンラインビジネスでは、専門部署の設置が難しい場合もありますが、外部の専門家の協力を得るなどして、適切な体制を整えることが重要です。
ITシステムの活用
近年は、本人確認や取引モニタリングを効率化するためのITシステムが数多く開発されています。
- AI技術を活用した不審取引の検知システム
- オンライン本人確認(eKYC)ツール
- 取引記録の自動保存・管理システム
- リスク評価支援ツール
これらのシステムを導入することで、人的ミスを減らし、効率的なコンプライアンス体制を構築することが可能になります。初期投資は必要ですが、長期的にはコスト削減にもつながります。
実務上の留意点
実務上、以下のような点に留意することが重要です。
- 本人確認手続きが顧客体験を損なわないよう工夫する
- 定期的なリスク評価とポリシーの見直し
- 法令改正への迅速な対応
- 従業員の意識向上と日常的なチェック体制の確立
特にオンラインビジネスでは、顧客の利便性とコンプライアンスのバランスをとることが重要な課題となります。
まとめ:オンラインビジネスにおける犯罪収益移転防止法の重要性
犯罪収益移転防止法は、一見すると事業者にとって負担に感じられるかもしれませんが、犯罪による収益の移転を防止し、健全な経済活動を守るための重要な法律です。特にオンラインビジネスの発展に伴い、非対面取引が増加する中で、その重要性はますます高まっています。
適切な対応は、単に法令遵守というだけでなく、企業の信頼性向上やブランド価値の保護にもつながります。顧客は安全で信頼できるプラットフォームを求めており、適切なコンプライアンス対応はビジネス競争力の源泉にもなり得ます。「わかりにくい」「負担が大きい」と感じる事業者も少なくありませんが、専門家のアドバイスを受けながら、自社の事業規模やリスクに応じた適切な対応を検討することが大切です。
また、犯罪収益移転防止法は定期的に改正されており、最新の動向を常に把握することも重要です。今後も国際的な資金洗浄対策の強化に伴い、さらなる規制強化が予想されるため、先を見据えた対応が求められます。
オンラインビジネスを健全に発展させ、犯罪に利用されない安全な経済環境を構築するために、事業者一人ひとりが犯罪収益移転防止法の重要性を理解し、適切に対応していくことが望まれます。
DOWNLOAD資料ダウンロード